今までの地元工務店の営業は、
- 社長中心型:すべての契約や見積もりを社長が担当
- 営業マン頼み:顧客情報や契約ノウハウを一人の営業マンが持っている
というケースが少なくありませんでした。
ですが、これは、工務店経営という視点から見れば、
- 社長がいないと営業も現場も進まない
- できる営業マンが辞めると売り上げが下がる
ということですし、
お客様側から見れば、
- 社長以外のスタッフに聞いても何もわからないみたいだ
- 聞く人によって言うことが違っていて、信頼できない
といったマイナスの感情が生まれやすくなります。
性能や価格では差がつきにくくなった今、信頼の基準は「人」から「仕組み」へ移っています。
そんな中、お客様が求めるのは、「誰が対応しても安心できる対応」です。
この一貫性こそが、これからの工務店が生き残る鍵とも言えるでしょう。
なぜ?「誰が対応しても安心」が大事なのか?
では、なぜ?「誰が対応しても安心」という「一貫性」が大事なのでしょうか?
理由は4つあります。
1、口コミ・紹介に差が出る
「〇〇さんじゃないと話が通じない。」
「担当が変わったら、不安になった。」
という状況は、お客様の信頼を「会社」ではなく「人」に集中させています。
つまり、会社への信頼度が下がるだけでなく、
結果的にお客様自身も、「口コミ、紹介」はしにくくなるのです。
なぜなら、口コミや紹介が、まるで「推し活」の押し売りのように見えてしまうからです。
2、ミスやクレームが減る
誰が対応しても同じという品質を保つためには、「情報共有」は必須事項です。
また、スタッフ間での「情報共有」への理解が進み、認識のズレがなくなると、結果的に、ミスやクレームも減っていきます。
さらに、お客様からの感謝の言葉や、心遣いをスタッフ全員で共有することにより、電話対応はもちろん、見学会や勉強会などでお会いした時の対応に変化が起こります。
つまり、マニュアル的に礼儀正しく接するのではなく、心温かなもてなしのオーラが生じるようになるのです。
(なぜなら、私たちは人間だからです)
3、チーム全体のレベルアップが早い
一人一人の個人的な経験がすべて、「仕組み」として還元されることになるので、チーム全体のレベルアップがどんどん進みます。
また、昔から「3人よれば文殊の知恵」という諺もある通り、チーム内から新しいアイディアや気づきを得られるため、スタッフ全員が自己成長していくことができ、それが、スタッフのやりがいや、会社のレベルアップにつながっていきます。
4、顧客満足が安定し、契約率が上がる
対応品質が「ブレない」だけでも、お客様に信頼されますが、
チーム=会社のレベルが上がること=他社が一朝一夕には真似できない差別化へとつながります。
「安心できる対応」は、見える化から始める
「安心できる対応」は、営業プロセスを見える化することから始めます。
営業プロセスが見える化すれば、おのずと、チーム全体で顧客対応ができるようになります。
営業プロセスの見える化の方法
誰が見てもわかるような、顧客情報、進捗、対応履歴を共有できるツールを作りましょう。
共有すべき事項としては、
- 問い合わせ日や、認知媒体、初回面談日、イベント参加の日付など
- お客様の基本情報(年齢、住所、電話番号、家族構成など)
- その時々の相談内容履歴(履歴が大事です)
- 雑談時に聞いたこと、話したこと
- お客様の嗜好、趣味
- その他
などが基本となります。
見える化のためには、特別なツールではなく、Officeなどの汎用ツールを使えば十分です。
どんなツールを作るか?は、それぞれの事情に合わせれば良いですが、
うまくいくポイントとして、前述した1~6の情報をすべて、一つの「ツール」に収めようとしない方が良いでしょう。
たとえば、
- データ系は、エクセルやスプレッドシートに。
- 相談履歴や、現場関連のものは、カルテに。
という具合です。
最初は、一つのカルテにすべて、納めた方が良さそうに思えますが、家づくりの場合には、情報量が膨大で複雑です。
そのため、分厚いカルテの中から、必要な情報を探すのに時間がかかってしまうケースも少なくありません。
目的に合わせ、カテゴリー分けをしておくのが良いと思います。
社内資料なので、実際に使うスタッフと相談しながら、よりよいツールに作り上げていきましょう。
まとめ
「誰が対応しても安心できる工務店」とは、要するに、「チームで顧客対応ができる工務店」ということです。
そして、チームで顧客対応ができる工務店になるには、まず「営業プロセス」を「見える化」することが必要不可欠です。
チーム対応のための営業プロセスの見える化は、「掛け声」や「ポリシー」も大切ですが、何より、実務レベルの「ツール」が必須です。
ツールを実際に使い続けることで、少しずつ、スタッフ間の共有が図られるようになりますので、まずは、簡単なツールを作成し、少しずつ形を整えていきましょう。
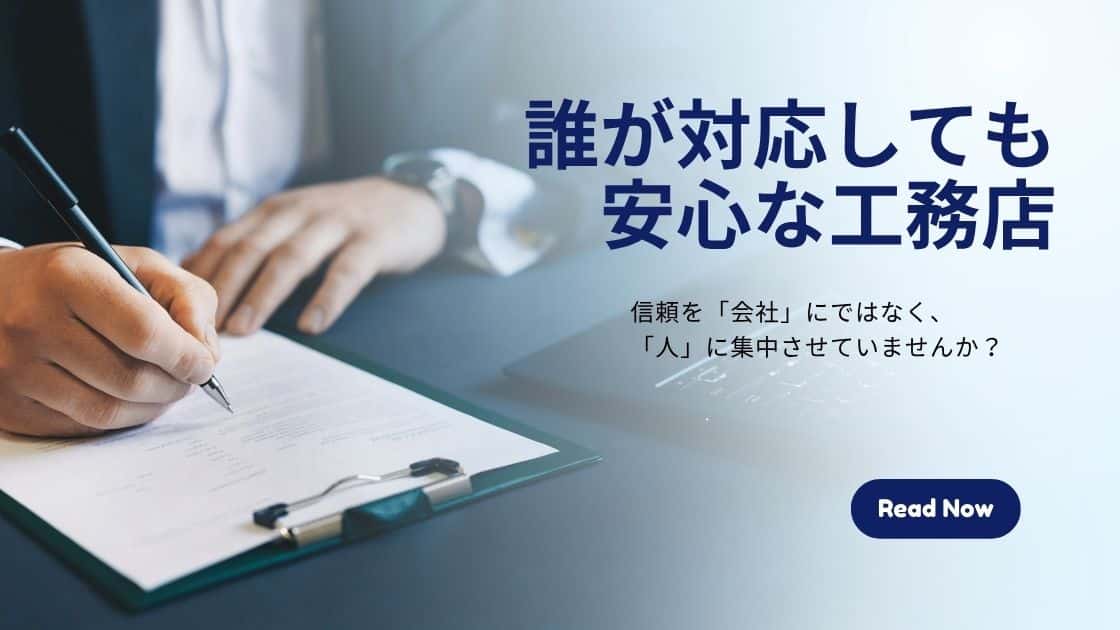


コメント